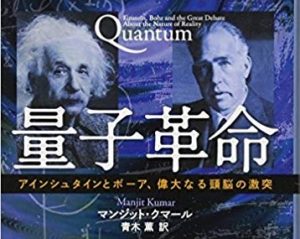自分と向き合う:「すらすら読める 徒然草」
『徒然草』は、 吉田兼好(兼好法師、兼好、卜部兼好)が書いたとされる随筆であり、清少納言『枕草子』、鴨長明『方丈記』とならび日本三大随筆の一つで、折々の兼好の心に浮かんだ思いを記したものです。
すらすら読める 徒然草
中野 孝次 (著)
講談社文庫(2013/11/15)
◆『徒然草』からの原文(243段)を、中野孝次が59段を選び抜いて“わが徒然草”を作りあげた。総ルビつきの原文と現代語訳、そして思いを込めた解説。南北朝の乱世を生きた兼好の永遠の古典が、時代を超え「今に生きる言葉」として蘇る。
兼好が隠棲したのは、31歳以前と考えられていますが、決して”世を捨てた”わけではなく、自分の心と向かい合うために「閑暇の中」に身を置いて、そこから静かに世の中を見たのだと思います。随筆ですので、テーマ毎に系統だって編んでいるわけではありませんが、「世俗」「趣味」「いい話」「名人」「仕事(芸)」「生き方」「死」「美」「趣味」「教訓」・・と、兼好の思索は様々な方面に及んでいきます。
今回は、その中から、「空虚よく物を容れる(第235段)」を紹介します。
「主ある家には、すずろなる人、心のままに入り来ることなし。主なき所には、道行人みだりに立ち入り、狐・梟やうの物も、人気に塞(せ)かれねば、ところ得顔に入り棲み、木霊(こたま)などいふ、けしからぬ形も現はるるものなり。また、鏡には色・像(かたち)なき故に、よろづの影来りて映る。鏡に色・像あらましかば、映らざらまし。
虚空よく物を容(い)る。我等が心に念々のほしきままに来り浮かぶも、心というもののなきにやあらん。心に主あらましかば、胸の中に、若干(そこばく)のことは入れ来らざらまし。」
(現代文意訳)人が住んでいる家には、用もない人間は入って来ないが、住む人の無い所には通行人が入り込むばかりか、狐やフクロウなどが住み着いてしまったりする。これらの事を見るにつけ、要は「空だからこそ、万物を入れることができる。」ということである。
すでに物が存在する所には、それ以上物を入れることはできない。それは「心」も同じことで、心が雑念(欲望、感情、空想・・)に占められていたら、想念が自由に出入りすることはできないだろう。部屋は絶えずまた空にしておかねばならず、人の心は絶えずまた無心にしておかなければならない。
かくいう私も、昨年、自ら社長職を辞していわゆる”閑暇”な生活に入ったわけですが・・今まで心の「容れ物」が、いかに仕事に占有されていたのかに改めて気が付きました。職にあった時は寸暇を惜しんでいろいろな本を読み研鑽を続けてきましたが、それは「仕事」でいっぱいになっている「容れ物」の隙間に、思索の一つ一つを”小間切れ”にして詰め込んで来たようなものだったのです。
そして、「仕事」が消えた後の「容れ物」の中では、今までの”小間切れ”が凄い勢いで次々とつながり、そして外からはまた新たな思索が入り込んでくる・・そんな感覚を今、実感しているのです。言うなれば、「思索は無限、されど”容れ物”は有限」と言ったところでしょうか。
とは言いつつも、そろそろ思索も乱雑になりかけているので、これからこのホームページを使って”整理”して、少なくとも、お客様には座布団の一つも敷いて差し上げるスペースぐらいは残しておきたいと思います。
これからは「私の研究室」で、「徒然草」を一つずつ採りあげてシリーズ化してみたいと思います。
『徒然草』とは・・
成立については、室町幕府の九州探題である今川貞世(了俊。兼好の弟子の命松丸と親交があった)が、兼好の没後、草庵に残っていた原稿を編纂したと言われてきたが、疑わしい。国文学者橘純一は、鎌倉時代末期、1330年8月から1331年9月頃にまとめられたとし、長く有力説とされてきた。この説によれば南北朝の争乱以前に中年期の兼好が著したことになるが、異論もある。現在は長年書き溜めてきた文章を1349年頃にまとめたとする説も有力になっている。
序段を含めて244段から成る。文体は和漢混淆文と、仮名文字が中心の和文が混在している。序段には「つれづれなるままに」書いたと述べ、その後の各段では、兼好の思索や雑感、逸話を長短様々、順不同に語り、隠者学の一に位置づけられる。兼好が歌人、古典学者、能書家などであったことを反映し、内容は多岐にわたり、また、兼好が仁和寺がある双が丘(ならびがおか)に居を構えたためか、仁和寺に関する説話が多い。 徒然草が伝える説話のなかには、同時代の事件や人物について知る史料となる記述が散見され、歴史史料としても広く利用されている。中でも平家物語の作者に関する記述(226段)は現存する最古の物とされる。
作品の名にもとられる書き出しの「つれづれ」(徒然)は「やるべき事がなくて、手持ち無沙汰なさま」を意味する。「つれづれなり」と「よしなしごと」や、「書き付く」は先行する文学にも用いられている組合せであり、作品および自己を卑下する謙遜の辞である。
執筆後約百年間は注目されなかったようで、同時代の史料に『徒然草』への言及は伝わらない。室町中期に僧・正徹が注目し、自ら書写した写本にこの作品を兼好法師のものとし、兼好の略歴も合わせて記している。これが正徹の弟子の歌人や連歌師たちに波及し、応仁の乱の時代に生きた彼らは、「無常観の文学」という観点から『徒然草』に共感をよせた。江戸時代になると、版本が刊行され、加藤磐斎の『徒然草抄』(1661年、寛文1年)、北村季吟の『徒然草文段抄』(1667年、寛文7年)といった注釈書も書かれていく。『徒然草』に記された教訓は町人などにも親しみやすく、身近な古典として愛読され、江戸期の文化に多大な影響を及ぼした。こうして『徒然草』は古典となり、文学史上の位置が確定した。写本は江戸時代のものが多く、室町時代のものは非常に少ない。(出典:Wikipedia)